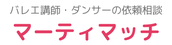- トップ
- バレエコンクール
- 海外オーディション
- 国内オーディション
- ダンサー・出演者募集
- バレエ留学
- ワークショップ
- 公演情報
- 公演レポート
- バレエ公演 Report GKB2024
- バレエ公演 Report えんとつ町のプペル
- リハーサル Report えんとつ町のプペル
- バレエ公演 Report エステルクリサ
- バレエ公演 Report 7 Dancing Crackers
- ダンス公演 Report TOKYO〜the city of music and love〜
- バレエ公演 Report Gala Vol.29
- バレエ公演 Report Gala Vol.28
- バレエ公演 Report Gala Vol.25
- バレエ公演 Report 音と舞うオータムコンサート
- バレエ公演 Report Gala Vol.23
- バレエ公演 Report えんとつ町のプペル
- アンサンブルガラコンサート2023
- バレエ公演 Report Gala Vol.21
- 緑公会堂フェスティバル
- バレエ公演 Report GKB
- アンサンブルガラコンサート
- バレエ公演 Report 音と舞うサマーコンサート
- バレエ公演 Report Gala Vol.16
- バレエ公演 Report Gala Vol.13
- バレエ公演 Report Gala Vol.12
- バレエ公演 Report Istanbul Fringe
- バレエ公演 Report Gala vol.11
- バレエ公演 Report NeRo
- バレエ公演 Report Gala Vol.10
- バレエ公演 Report Gala vol.9
- バレエイベント
- オンラインバレエ
- バレエ情報
- 書籍・映画・TV・動画情報
- Balletweek Magazine
- お問合せ
- 広告掲載
- バレエイベント広告宣伝サービス

NEW 7.31 更新

帰国した私に「松山バレエ学校の教師」という話が…。
そんな事を夢にも思っていなかった私は大変困惑した。ただ知っているバレエのステップを教えるのが「先生」のはずがないからだ。私の意思を他所に話はどんどん進んでいた。そして気づいてみたら、自信の無さを悟られまいと生徒の前で必死に振る舞う自分がいた。
「先生」と呼ばれる事に違和感を覚えながら「本当に自分で良いのか?」と自問自答しながら緊張の日々が続いた。私の気持ちとは裏腹に、私の見本を疑い1つないキラキラした瞳で見てくれる生徒の純粋さに心が乱れた。
そんな時「バレエの神様っていたのだ!」と思う出来事が…。
松山バレエ学校に、10歳過ぎてからでもバレエを習う事が出来る「初等Cクラス(現在のベーシッククラス)」が誕生したのだ!
そして…何と!担当教師に私の名前があった。
第1章での私がバレエ学校の門を叩いた時の経緯などは誰も知らなかったのに…。私の生きる道はここにあるのだと確信した瞬間だった。
それから間もなくの事、バレエ団の階段で松山樹子先生に声をかけられた。
「何故舞台に出てないの?」何故?と言われて言葉につまっていた私に、「光を浴びなさい!」「光を浴びなければダメ!」
松山先生は、私の毎日の行動を見ていた訳もなく、ただ通りすがりに私を見かけた直感で全てを見抜く人なのだ。
数日後、再び松山先生から「私と一緒に来なさい。」と稽古場へ…そしていきなり「パドカトルを踊ってごらんなさい」と。
パドカトルといえば歴史上最も古い作品で、松山バレエ団プリマ森下洋子先生が東洋人として初めてパリオペラ座の舞台で踊った尊いもの…
松山先生とのリハーサルは夜中まで続く日もあった。そしてこの作品を携え、先生と2人、バレエを広めに出かける事となった。大企業から都立高校と何ヵ所も回った。
翌年、有楽町駅前に5000人規模の劇場が完成した。そのこけら落としに松山先生振り付けでの出演が決まり…
舞台活動を離れて以来、止まっていた私の中の時計が動き出した。
バレエ団現役時代、仕事仕事で私の舞台を観に来た事が無かった父だったが、初めてこの舞台を観に来て一言、「こういうのを親孝行って言うのかな?」と。それが最初で最後の親孝行になってしまった…。
「光を浴びなければダメ!」
松山先生の言葉の意味を追いかけながら生徒達と向き合う日々の中で、ようやく気づいたのだ。先生になる自信が無かったのではなく、自信をつける為の努力をしていなかった事に…。
「教える場」は「教わる場」でもある事を、かけがえのない大切な生徒達から学び、共に成長して行くのだと…。
松山バレエ団OBの松本亮先生とのご縁を戴き、インドネシア伝統芸術に触れる機会も与えられた。
ガムラン(民族音楽)の生演奏をバックに、夜を徹して踊る様を舞台表からは影絵として、舞台裏からは実際の踊り手を見る事が出来る。
こんなにもエキゾチックな世界があるのだと心が震えた。
バレエ団の舞台は勿論の事、松山先生と出かけたワークショップ、クラシックバレエ以外の舞踊…。
バレエ教師としてだけでなく、様々な勉強の機会を惜しげも無く与え、まだ足りない、まだまだだ!と叱咤激励を今現在も…。
松山バレエ団に入らなければ、母があの時松山バレエ学校を選ばなければ、私はとっくにバレエから離れていただろう。
長きに渡り1つの事を続け、一所に身を置くのは簡単ではない。
求められるからではなく、自らが求めるからこそ、そこにいる価値があるのだと…。
「今、私が伝えたい事」それは…
どんなに時代が移り変わろうとも「感謝」を忘れなければ、どんな困難も乗り越えられるだろう。
時にバレエの神様は私達に問いかける…その問いかけにそっと目を閉じて耳を澄まし、勇気を持って答えたら…必ず夢は叶うと信じていたい。
これからもずっと…。
最後に、
今回のバレリーナインタビュー独占取材の連載を受けて自分自身を振り返る機会を与えられた事に、そして今までこんなにもたくさんの出会いに支えられていた事に、抱えきれない程大きな愛に感謝を捧げたい。
第1章から最終章までお読みくださった皆様、本当にありがとうございました。
小川 麻乃
※記事の文章及び写真を無断で使用することを禁じます。

NEW 6.28 更新

初めて踏み入ったバレエ団公演の舞台裏。バレエ学校発表会では見慣れた楽屋だったが、いざ公演となるとその表情は一変、張りつめた空気、普段は気さくな団員の先生方もその目線の先に「聖域」のようなものを感じた。
今まで客席側からしか観た事のなかった美しい舞台…そして初めて観た舞台裏からの全て…
先ず驚いたのは、楽屋入りから劇場を出るまで舞台スタッフ、出演者全員が一丸となって舞台創りに取り組む姿だった。手伝いに来たはずの時間だったが、役に立つどころか何をしたのかも覚えていないほど、その空気に圧倒され続けた。
その日から3ヵ月が過ぎた頃、バレエ団の掲示板に「くるみ割り人形全国ツアー公演」配役表の片隅に自分の名前があった!そして名前の横に「ST」と書かれていた。スタンバイという意味なのだと後に知った。名前はあったが、誰からも何の指示も話もない。どうすれば良いのかもわからず、今までガラス越しにしか見た事がなかった公演リハーサルの開始時間に恐る恐る入り「配役表に名前があったのですが、参加してもよろしいでしょうか?」と尋ねると「自分で考えれば?」と…。
今思うと、その日から私は松山バレエ団員になったのだ。
そして厳しい日々の幕が開いた…年間通して休みはたったの4日ほどしか無かった。東京を中心に北海道から九州まで全国を公演して回った。そのような中東北公演前日のある日、前々から左腕と左手首に正体不明のひどい発疹が出ていたが、テーピングで隠してリハーサルに出ていた。ずっと気になっていたのか、とうとう総代表に「その腕見せてみろ」と言われてしまった。やっとやっともらった白鳥の役だった…。見せたら役を下ろされ、明日からの旅公演が…!ところが普段は厳しい先生が「早く病院行け!」と言ってくれた。診断は帯状疱疹、入院を勧められたが私にとっては旅公演に行かない選択肢は0だった。

東北の次は東京公演、そしてまた関西へ…
地方の劇場での「出待ち」で少女にサインを求められてとても困った事…
どの公演も超満員の客席から沢山の拍手…
待ちに待った「眠れる森の美女」の衣裳が船で到着した時の感動…
そして初めて立ったヨーロッパの劇場…
どれも松山バレエ団にいなければ出来なかった尊い経験だった。
時間にも気持ちにも余裕のない日々だったが、バレエ団で踊れる喜びがその全てを吹き飛ばした。
吹き飛ばした…そう思い込んでいた。そう思おうとした。
しかし、私の貧弱な精神はもはや限界に来ていた。
あれほど憧れ、夢にまで見た中に自分がいる…それなのに苦しい…心と身体がバラバラになり始めているのを感じた。
元々あまりバレエ団活動には前向きでなかった両親に苦しい姿を絶対に見られたくなかった。
そんな娘の様子を気づかない訳もなく、活動休止を迫られた。
そして私は、ドイツで音楽活動をしている姉のもとへ向かう決断をした。
松山バレエ団以外のバレエがどのようなものなのか確かめるべく、姉の力を借りながらドイツ国内の州立劇場のバレエ団を回って歩いた。隣国スイスのバレエ団の友人宅を拠点にオランダまで足を伸ばした。ドイツ語は愚か、英語も出来なかったが不思議とどこのバレエ団でも困る事は無かった。
理由は簡単だ。バレエ用語は全てフランス語だから、どこに行っても共通なのだ。
そんなある日、姉と共に住んでいた女子寮の食堂で「ベルリンの壁が崩れた」という衝撃的なニュースを目にした。姉の仲間にも旧東ドイツから亡命してきた友人がいた。皆、国境警察に何度も捕まりながらも自由な芸術活動を求めて命懸けだったのだ。
それに比べて私は…
平和な国に生まれ、愛情に満ちた家庭、そして大好きなバレエ団で活動の場を与えられていたにも拘わらず…
そんな思いを胸に帰国した。
帰国した私に待っていたものは…
夢の先にあった現実…それは、感謝の気持ちを忘れてしまった自身の姿だった。
☞第4章へ続く(7月配信予定)
※記事の文章及び写真を無断で使用することを禁じます。
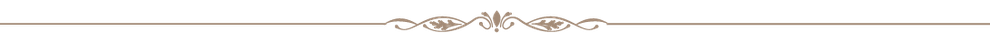
NEW 5.26 更新

バレエを始めて劇的に変わった事、それは「食」だった。今までは食事の時間が恐怖に感じる程食が細く、よく父からは「洗濯板」(→今や時代劇でしか実物を見るのは難しい)と呼ばれていた。それがいつしか食事の時間が待ち遠しく、母の手料理がこんなにも美味しかったのかと自分でも驚いた。
夢にまで見たバレエのお稽古は、思い描いていたものとはだいぶ違っていた。地味な動作の繰り返し…。そんな動きさえもままならない日々だったが、先生は忙しい合間に私達生徒をバレエの映画に連れて行ってくれたり、時には厳しく叱ってくれた。そして松山バレエ団の美しい舞台を観に行く度に「私もいつかあの場所に…」愛情に満ちた2年間が更に私を夢中にさせた。
いよいよ松山バレエ学校の門を再び叩く。2年前の古い建物から立派なお稽古場に生まれ変わっていた。私が入った中学生クラスは皆3歳4歳から進級してきたレベルの高い生徒たち…松山バレエ団総代表自らクラスに出向き、熱い指導を行う日もあった。そんな中で、自分が何も出来ていない事も、何がわからないのかも気づかない…まわりとの差はかなりなもので、だいぶ浮いた存在だったと思う。皆に追いつこうと稽古日を増やしたものの、なかなか思うように身体は動かず、頭も回らず、いつしか「私はやはりバレエに全く向いてないのでは?」と考えるようになっていった。
今思えばたかだか3年や4年で思うように踊れる程バレエは簡単ではない。そもそもバレエに向いているとは何か?と聞かれたら、今なら迷わずこう答える。「向いていない人などいない、継続出来るか出来ないか、それに尽きる」と。
バレエを始めて5年が過ぎた。
高校生になると、バレエ学校最高学年のクラスに進級する事になるが、同学年の友達が皆進級して行く中、1人取り残された…。
新学期が始まって、小学生クラスから進級してきた子達と一緒のお稽古…。不思議にも疎外感や劣等感等そこには全く無く、自然に溶け込めたのも松山バレエ学校の校風に他ならない。いつもそこには温かい愛情があった。
しかし…最高学年クラスに進級してからは厳しさを強く感じる日々。目の前には準団員のクラスが控え、皆目標に向かって必死だった。
バレエを始めて以来、初めて「苦しい」と思った。好きな気持ちは変わらずあったが、バレリーナになりたいという夢はもはや「妄想」と化していた。このまま続けていても…と度々考えるようになり、いつしかバレエ学校に向かう足どりも重くなっていった。
重くなったのは気持ちだけでなく体重もだった。高校のクラスメイトと学校帰りにドーナツを食べるのがほぼ日課になり、1日で10個食べた日もあった。最高学年の厳しいクラスでは、私が何kg太ろうが誰も何も言ってくれない。
母からの耳の痛い小言には幼稚な反論をならべて現状を認める事は無かったが、いざ体重計にそっと乗ってみて愕然とした。
やはり何事も自分自身で気付き、認めなければ先には進めないのだ。大好きなドーナツもやめて気持ちも新たに出直し、進路を決める歳になった。勇気を持って両親に「実力的には難しいが、バレエ団に入りたい」と。どうやって入団出来るのかも良くわからないままだったが、両親は「ダメでも良いからやれるところまでやりなさい」と言ってくれた。
大きな理解と愛情を胸に朝のクラスに進級した。
このクラスはバレエ団の舞台で既に活躍している若手と、私のように最高学年クラスからバレエ団に入りたくて進級した生徒がいる。
新学期から1ヶ月、いつものように朝のクラスを終えて、仲間たちと帰ろうと外に出た時、2階の窓からバレエ団総代表に呼び止められた。私?半信半疑で稽古場に戻ると…
「今日これから劇場入りするんだけど、時間空いてる?手伝いに来ないか?」と!!!
奇跡が起こったのだと思った。
その日は約束があったが、「空いてます‼」と即答した。今のように携帯電話などない。約束はすっぽかした。
苦しさの先に見えたもの...それは夢が夢でなくなるかも知れない未来だった。
☞第3章へ続く(6月配信予定)
※記事の文章及び写真を無断で使用することを禁じます。

NEW 4.28 更新

1971年、6歳の時に初めて観たバレエ「白鳥の湖」。今、正に悲しい出来事の中にある「ボリショイ、レニングラード合同公演日本ツアー」だった。この世に生まれてたったの6年しか経っていない少女の目に、そのあまりに美しい夢の世界が彼女の人生を大きく変える事になる程衝撃的に映った事は言うまでもない。
その日を境に毎日「バレエを習わせて」と母にお願いするも決して叶う事はなく、気がつけば4年もの間日課のようにお願いし続けたある日…「あなたには根負けしたわ」と母からの言葉。諦めかけていた胸の奥に押し込めていた思いが爆発した瞬間だった。
この日の週末、逸る気持ちを抑えながら松山バレエ学校の門を叩く!
扉を開けると今まで嗅いだ事のない素敵な匂いと共に聞こえてきたトウシューズの響き...そして次の公演に向けてであろうリハーサルをしていた松山バレエ団の美しいバレリーナ達の姿にただただ呆然と見とれていた…
母はしきりに稽古着姿の男性と話をしていて、その表情は困惑しているように見えた。話が終わり「帰りましょう」と母の表情で何か嫌な予感、今考えれば当然だったのかも知れない事実を突き付けられた。
当時10歳、身長も既に150㎝近くまでに成長していた私に入学できるクラスは無く…(その15年後に「バレエの神様っていたのだ‼」と確信するような驚く出来事が…)結論は厳しいものだった。
肩を落としてバレエ団を出ようとした時、「待って下さい、住所を見たらお宅のそばで私、お稽古場を開いたばかりです。よろしければバレエ学校に通えるようになるまで習いに来ませんか?」
リハーサル途中に走って来た額の汗がキラキラに輝いていて「なんて美しいバレリーナ」...
絶望から一気に光を与えてくれた私にとって最初の先生との出会いだった。
ただ、近所というには少々遠く、バスと電車に乗り継いで1時間、それでもお稽古日を心待ちにする日々だった。
諦めなかった先にあったもの…それは、夢への第1歩だった。
☞第2章へ続く(5月配信予定)
※記事の文章及び写真を無断で使用することを禁じます。

バレエ総合情報サイト・バレエウィーク / Ballet-Week Japan のサイト。全国のバレエコンクール、バレエ団のオーディション、バレエ留学・エージェント情報、バレエ公演情報、ワークショップや特別レッスのニュースが満載。バレエ・ダンサー募集・出演者募集情報も。海外留学、海外のバレエ団やカンパニーを目指す方、プロダンサー・フリーのダンサーの為のバレエ業界情報収集やレベルアップに。ビデオやオンラインオーディション・審査情報も配信中。
Ballet general information site Ballet-Week Japan site. Full of news on ballet competitions, ballet company auditions, ballet study abroad / agent information, ballet performance information, workshops and special lessons nationwide. Information on recruiting ballet dancers and performers. For studying abroad, those who aim to become an overseas ballet company or company, and for collecting information and improving the level of the ballet industry for professional dancers and freelance dancers. Video and online audition / examination information are also being distributed.
マーティグループのバレエ・ダンス情報サイト一覧
スタジオマーティ・バレエスクールは、東京・大阪・横浜・川崎・福岡で大人と子供のバレエ教室を運営しています。国際的な文化芸術体験を大切に。バレエやダンスは子供や幼児・園児の習い事、運動、趣味、教育、表現力、柔軟性、音感リズム感トレーニングにも最適です。女の子はもちろん、男の子にも人気。高品質なレッスン、バレエに最適な床やスタジオ環境、リーズナブルでわかりやすい料金体系、振替対応、オンラインレッスン充実。キッズ・ジュニアクラス、英語クラス、親子バレエ、リトミック、ダンスレッスン、チア、テーマパークダンス、シアタージャズ、ジャズバレエ、トウシューズクラス。発表会、季節イベント、地域イベント、お祭り、舞台出演や発表の機会が沢山。コンクール指導、プレコンクール、個人・プライべート指導やバリエーションクラスなど本格的なクラスも充実、成長レベルに合わせて積極出場。名門バレエ団・名門スクール出身講師、バレエ経験・留学経験豊富な専門スタッフ。英語でバレエ、English ballet、バイリンガルクラス、本場を学べる海外ゲスト講師による特別クラス、留学サポートサービス。幼児、幼稚園、保育園、インターナショナルスクール生も多数在籍。講師やプロダンサーが出演する舞台への鑑賞ツアーなど。いつから始めても大丈夫。バレエ・ダンス情報満載の本格的に楽しく学べるバレエスタジオです。
Studio Marty Ballet School operates ballet classes for adults and children in Tokyo, Osaka, Yokohama, Kawasaki and Fukuoka, Japan. Valuing an international cultural and artistic experience. Ballet and dance are also ideal for children, toddlers and kindergarten lessons, exercise, hobbies, education, expressiveness, flexibility, and perfect pitch training. Popular with boys as well as girls. High-quality lessons, optimal floor and studio environment for ballet, reasonable and easy-to-understand fee structure, transfer support, and online lessons. Kids / Junior Class, English Class, Parent-Child Ballet, Rhythmic, Dance Lesson, Chia, Theme Park Dance, Theater Jazz, Jazz Ballet, Pointe Shoes Class. There are many opportunities for recitals, seasonal events, regional events, festivals, stage appearances and presentations. Full-scale classes such as competition guidance, pre-contest, individual / private guidance and variation classes are also enriched, and actively participate according to the growth level. Instructors from prestigious ballet companies and prestigious schools, professional staff with abundant ballet experience and study abroad experience. Ballet, English ballet, bilingual classes in English, special classes by overseas guest instructors who can learn the real thing, study abroad support service. Many infants, kindergartens, nursery schools, and international school students are also enrolled. Appreciation tours to the stage where instructors and professional dancers appear. It's okay to start anytime. It is a ballet studio where you can enjoy learning in earnest with lots of ballet and dance information.
スタジオマーティ・バレエオンラインレッスン / STUDIO MARTY BALLET ONLINE LESSON
マーティのバレエのオンラインレッスンです。zoomアプリで自宅やご家庭から、1クリック簡単接続。大人から子供までのバレエバーレッスン、バレエダンサーのトレーニングやストレッチ、家でのケア方法などライブ配信やレッスン動画、無料動画を多数配信。受講方法や料金も簡単。キッズ向けレッスン、大人バレエ、オープンクラス、ポワントクラス、バリエーションクラス、ストレッチクラス、バーレッスン、初心者入門クラス、親子バレエなど多数開講中。海外のゲストダンサー・講師、現役プロダンサー・有名講師多数在籍のスタジオマーティのオンラインバレエ講座を紹介しています。幼児向け、子供向け、小学生向け、大人向け、OL、社会人の運動、習い事にもレッスン充実。バレエやダンスは子供や幼児・園児の習い事、運動、趣味、教育、表現力、柔軟性、音感リズム感トレーニングにも最適です。バレエに加え、ヨガ、ピラティス、ジャイロキネシス、バレトン、ジャズバレエ、キッズヨガ、キッズダンス、テーマパークダンス、解剖学などの座学講座も開講中。スマホで受講も可。レッスンのやり方、システムや料金設定など、わかりやすく受講しやすいオンラインレッスンです。
Marty's ballet online lesson. Easy one-click
connection from home or home with the zoom app. We deliver a lot of live distribution, lesson videos, and free videos such as ballet lessons for adults and children, training and stretching of
ballet dancers, and care methods at home. Easy to attend and fees. There are many lessons for kids, adult ballet, open class, pointe class, variation class, stretch class, bar lesson, beginner
introductory class, parent and child ballet, etc. Introducing the online ballet course of Studio Marty, which has many overseas guest dancers / lecturers, active professional dancers / famous
lecturers. There are plenty of lessons for toddlers, children, elementary school students, adults, office ladies, adult exercise, and lessons. Ballet and dance are also ideal for children,
toddlers and kindergarten lessons, exercise, hobbies, education, expressiveness, flexibility, and perfect pitch training. In addition to ballet, classroom lectures such as yoga, Pilates,
gyrokinesis, ballet, jazz ballet, kids yoga, kids dance, theme park dance, and anatomy are also available. You can also take classes on your smartphone. It is an online lesson that is easy to
understand and take, such as lesson methods, systems and pricing.
関連教室
関西エリア 大阪: 大阪本町スタジオ 阿倍野バレエスクール 梅田東バレエスクール 大阪梅田バレエスタジオ 天王寺バレエスクール 天満橋バレエスクール 西本町バレエスタジオ 茨木バレエ教室 高槻バレエ教室 豊中バレエ教室 吹田バレエ教室 堺バレエ教室 新大阪バレエスクール 難波バレエ教室 東大阪バレエ教室 野田バレエスクール 都島バレエスクール 北浜バレエスクール 福島バレエ教室 千里バレエスクール 谷町バレエスクール 大阪・豊崎バレエスクール 大阪・城東バレエ教室 上本町バレエスクール 大阪本町レンタルスタジオ 大阪堺レンタルスタジオ 大阪チアダンス教室
兵庫: 尼崎バレエ教室 西宮バレエ教室 芦屋バレエスクール 神戸・御影バレエ教室 神戸・本山バレエ教室 神戸バレエスクール 京都: 京都バレエスクール 福岡: 福岡・天神バレエ教室 福岡薬院バレエ教室 福岡赤坂バレエ教室
関東エリア 東京: 東京三田慶応スタジオ 駒沢大学スタジオ 品川シーサイドバレエスタジオ 品川バレエスタジオ 東京池袋バレエスタジオ 新宿バレエスタジオ 東京・大塚バレエ教室 錦糸町バレエスタジオ 築地バレエスタジオ 町田バレエスタジオ 鶴川バレエ教室 国分寺バレエ教室 三鷹バレエ教室 月島バレエスタジオ 勝どきバレエスタジオ 勝どきレンタルスタジオ 築地レンタルスタジオ 立川バレエスクール 八王子バレエスクール
神奈川: 新横浜スタジオ 横浜反町スタジオ 戸塚バレエ・ダンス教室 横浜バレエスタジオ 横浜関内バレエスタジオ 中山バレエ教室 溝の口バレエ教室 武蔵小杉バレエスタジオ 川崎バレエスタジオ 相模原バレエスクール
オンラインバレエ・スタジオマーティオンライン マーティ・ピアノ教室 マーティマッチング バレエ留学支援サービス バレエコンクール情報
マーティプレバレエコンクール プレコン東京 プレコン横浜 プレコン埼玉 プレコン大阪 プレコン京都 プレコン神戸
みんなのバレエガラコンサート ガラコン東京 ガラコン横浜 ガラコン大阪 ガラコン川崎 ガラコン神戸 ガラコン京都
Related School
Kansai Area Osaka: Osaka Honmachi Studio, Abeno Ballet School, Osaka Umeda Higashi Ballet School, Osaka Umeda Ballet Studio, Tennoji Ballet School, Tenmabashi Ballet School, Nishihonmachi Ballet Studio, Ibaraki Ballet Class, Takatsuki Ballet Class, Toyonaka Ballet Class, Suita Ballet class, Sakai Ballet Class, Shin-Osaka Ballet School, Nanba Ballet School, Higashi-Osaka Ballet School, Osaka Noda Ballet School, Miyakojima Ballet School, Kitahama Ballet School, Osaka Fukushima Ballet School, Senri Ballet School, Tanimachi Ballet School, Osaka Toyosaki Ballet School, Osaka Joto Ballet School, Uehonmachi Ballet School, Osaka Honmachi Rental Studio, Osaka Sakai Rental Studio, Osaka Cheerdance School
Hyogo: Amagasaki Ballet School, Nishinomiya Ballet School, Ashiya Ballet School, Kobe Mikage Ballet School, Kobe Motoyama Ballet School, Kobe Ballet School
Kyoto: Kyoto Ballet School, Fukuoka: Tenjin Ballet Class, Fukuoka Yakuin Ballet Class, Fukuoka Akasaka Ballet,
Kanto Area Tokyo: Tokyo Mita Studio, Komazawa Studio, Shinagawa seaside Ballet Studio, Shinagawa Ballet Studio, Ikebukuro Ballet Studio, Shinjuku Ballet Studio, Tokyo Otsuka Ballet, Kinshicho Ballet Studio, Tsukiji Ballet Studio, Machida Ballet Studio, Tsurukawa Ballet Class, Kokubunji Ballet Class, Mitaka Ballet Class, Tsukishima Ballet Class, Kachidoki Rental Studio, Tsukiji Rental Studio, Tachikawa Ballet School, Hachioji Ballet School,
Kanagawa: Shinyokohama Studio, Yokohama Tanmachi Studio, Totsuka Ballet Dance Class, Yokohama Ballet Studio, Yokohama Kannai Ballet Studio, Nakayama Ballet Class, Mizonokuchi Ballet Class, Musashikosugi Dance Studio, Kawasaki Ballet School, Sagamihara Ballet School
Online Ballet Lesson / Studio Marty Online, Marty Piano School, Marty Ballet Matching service, Ballet Passport, Japan Ballet & Dance Information Portal
Marty Ballet Competition in Japan, Ballet Gala Civic Concert, Ensemble ballet gala concert